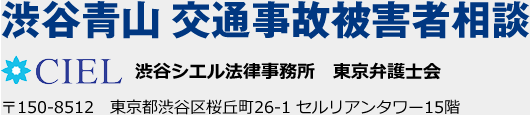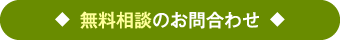【弁護士コラム】その⑦ 買取価格
ただ、手放すそのときまで、愛車ベンツの武勇伝は続きます。
職業柄、破産管財人も勤めることがあるため、少しでも高く売らないと誇りが許さず、このときも、中古車買い取りの専門店に何社か問い合わせをしました。 ところが、「この車は右ハンドルのため、外国で売れない。「赤のベンツを乗る人は日本には余りいない。」などと言われ、当初、殆ど値が付きませんでした。
ところが、知り合いの動産引き取り業者が、愛車を見てくれて、「このC220のベンツは、生産台数がそれ程多くないので、マニアが欲しがる傾向がある。」 と言ってくれました。
最後は、そう言ってくれた動産買い取り業者ではなく、その社員さんに個人的に引き取って貰ったのですが、車の買い取り業者が付けた値 の倍ので引き取ってくれました。きっと今も大事に乗ってくれているはずです。そんな色々なエピソードのある愛車でした。
車好きは封印
元々、私は、大学時代、運転免許を取ったその日に首都高速に乗ったという車好きです。なので、今後、機会があったらまたお気に入りの車を見つけ出して趣味として運転を楽しむかもしれません。今のところ小休止です。

高齢社会となり、65歳以上の高齢者が被害者となるケースも良く見られるようになりました。「お客様の声」にコメントを寄せて下さった「60代女性A.M様」もそのお一人です。
この方は、新車を購入直後に追突事故に遭って、当初は、物損示談のご相談だけでした。お怪我については、「毎日リハビリに通っているので直ぐに治ると思います」と仰っていたのですが、頸~腰の痛みや頭痛といった、むち打ちの症状が長引き、結局、後遺症が残ってしまいました(後遺症の申請をしたところ、後遺障害等級14級が認定され、この等級を前提に人身損害に関する示談をしました)。
この方のように、高齢になると、たとえ軽症であっても、予想以上に症状が長引き、後遺症が残ることが多いです。良く聞くのは、「もうこの歳になったら、あちこちガタがきてるので、治るか不安です。」とか、「お医者さんからも、年齢が年齢なので、元の状態に戻るのは難しいと言われている。」というお声です。
このように、高齢の方の場合には、後遺症が残るケースが多いです。
この他にも、高齢の方特有の問題として、一般に、次の3点が指摘されています。
第一に、既往症があるケースが多いため、賠償額を減額すべきという、いわゆる「素因減額論」が、加害者側から主張されるケースが多い事。
第二に、死亡した場合の慰謝料について、若年者より低額であるべきだと主張されるケースがある事。
第三に、無職である事が多いため、後遺症逸失利益(事故によって喪失した得べかりし利益)はないと主張されるケースが多い事です。
つまり、賠償金の減額要素が増えるのです。
しかし、第一については、例えば、大腿骨骨折の傷害を負ったところ、高齢により骨粗鬆症が進行して骨折し易い状態にあったとの理由で、賠償額を減額すべきだと主張されたケースについて言うと、高齢になればなる程骨粗鬆症の有病率は高まるわけで、高齢者にとっては普通の状態である骨粗鬆症という「素因」を理由に減額するなどということは、あってはなりません。
第二の死亡慰謝料については、誰もが年齢にかかわらず生きる喜びを享受すべきである以上、死亡による慰謝料が年齢によって違うというのは暴論です。
第三の逸失利益については、高齢でも元気に働き高額な収入を得ている方は沢山いるので、高齢であるから逸失利益がないと断定することは出来ません。
したがって、高齢被害者であっても、具体的なケース毎に、あるべき正当な賠償金を検討すべきで、実際にも、裁判実務では、たとえ加害者側から色々な減額事由が主張されたとしても、個々のケース毎に、具体的な事実認定と評価が行われています。
当事務所の弁護士である、小林のコラムです。
是非ご一読下さい。
お気軽にお問合せ下さいませ
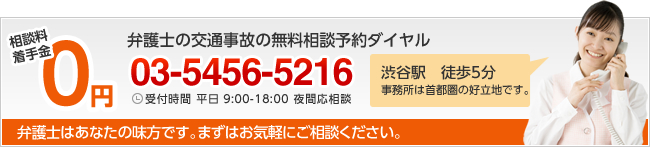
| ●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |