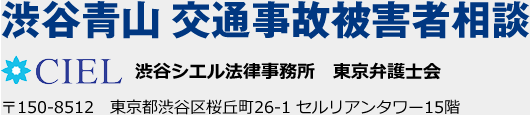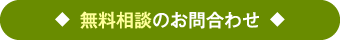【弁護士コラム】交通事故の被害者が陥りがちな誤解①
交通事故の被害者が陥りがちな誤解①
―「可動域制限=後遺障害」ではないという現実―
 交通事故に遭い、バイクや自転車で転倒してしまった際、多くの被害者の方が脚(下肢)に重大なケガを負うことがあります。
交通事故に遭い、バイクや自転車で転倒してしまった際、多くの被害者の方が脚(下肢)に重大なケガを負うことがあります。
とくに股関節、膝関節、足関節といった「下肢の三大関節」を負傷した場合、入念な治療を受けたとしても、痛みや可動域の制限といった不具合が後に残ってしまうケースは少なくありません。
そして、そのような不具合を抱える被害者の多くが、「事故前のように膝が曲がらなくなった」という理由で、自賠責保険の後遺障害等級の認定を目指すことが多い印象です。しかし、ここに一つ大きな誤解が潜んでいます。
「曲がらない」だけでは後遺障害と認められない
自賠責保険における後遺障害の等級認定には、厳格な基準があります。
たとえば、膝の可動域が健側(=負傷していない側)の1/2以下あるいは3/4以下に制限されているなど、客観的で明確な数値基準を満たしていなければ、「機能障害」として認定されることはありません。つまり、「以前より動かしにくい」「ちょっとしか曲がらない」という主観的な訴えだけでは、認定は極めて困難なのです。
被害者の方がこうした厳しさを知らずに、「下肢の後遺障害」→「機能障害(=可動域制限)」という文言だけを頼りに申請を進めてしまうケースは、実務でも少なくありません。
実は「痛み」による認定の方が現実的な場合も
一方で、可動域制限と並んで残ることが多いのが「痛み」です。膝や股関節などに慢性的な疼痛が残る場合、それが「局部に頑固な神経症状を残すもの」あるいは「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級または14級に認定される可能性があります。
とくに、12級の認定を受けるためには、医師の診断やMRI、X線などの他覚的所見が求められますが、症状と医学的所見が一致していれば認定されるケースは少なくありません。可動域制限だけに固執するよりも、痛みという観点からも後遺障害の申請を準備することが、認定の可能性を広げるカギになるのです。
【2025年7月1日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
その後、ヨーロッパ旅行に出掛けた際、イギリスのロンドンで、何台か自分と同じ真っ赤なベンツを見かけましたが、驚いたことに、いずれも白髪のお爺様が運転していました。
これにはビックリしましたが、一緒に見ていたJALのパイロットさんが言うには、「そうですよ。日本と違って、ヨーロッパでは、年配の人程、派手な色を好むんです。生き生き見えませんか?すてきな文化ですよね。」と解説してくれました。
確かに運転していた年配の男性は洒落ていて、生き生きと若く見えました。外国の人は洋服も、年配の方ほど、綺麗で派手な色を好むようですが、着ているご本人も気分が明るくなるでしょうし、見ていても大変若々しく綺麗に見えるものです。文化の違いですね。
Part1 公認会計士になろう!
 今年(2018年)の4月、長く拝命していた東京家庭裁判所の調停委員を退任して時間が出来たのを機に、ふと、公認会計士になろうかな?と思い立ち、良い受験予備校を探さねばと、知り合いの会計士等に相談したところ、「色々あるけど小林先生のオフィスが入っているビルの裏にTACの渋谷校があるのでは?」と言われてびっくり。
今年(2018年)の4月、長く拝命していた東京家庭裁判所の調停委員を退任して時間が出来たのを機に、ふと、公認会計士になろうかな?と思い立ち、良い受験予備校を探さねばと、知り合いの会計士等に相談したところ、「色々あるけど小林先生のオフィスが入っているビルの裏にTACの渋谷校があるのでは?」と言われてびっくり。
そう言えば、確かに「資格の学校TAC」と書かれた巨大な赤看板が掲げられておりました。人間って興味がないものは目に入らないのだ。と我ながら呆れつつ、善は急げと渋谷校の門を叩きました。といってもエレベータで5階の受付に行っただけですが、受付では「S田さん」という若い男性が対応してくれました。
この「S田さん」、最近まで事件の相手方だった切れる若手弁護士「S田」と同じ名前だったので、一瞬不快な思い出が蘇りましたが、気を取り直して色々聞くと、弁護士資格を持っている(=司法試験の合格証書を持って行く)だけで試験科目のうち民法と企業法が免除+短答試験も免除=受講料も免除されるのだそうで、WEB通信1年コースだと、通常60万円~70万円の受講料が45万円程に減額されるとのこと。
日本の弁護士資格は万能の資格と言われるだけあって、受験が必要な公認会計士資格でもこんなに優遇されているのか!と、無知を恥じつつ有難さに浸り、そういうことならば弁護士は皆、会計士試験も受験して会計士資格も持てば良いのに!と、このときは本当にそう思いました。その後、そんな思いは吹き飛ぶのですが・・・。その点はまた後日。(続く)
お気軽にお問合せ下さいませ
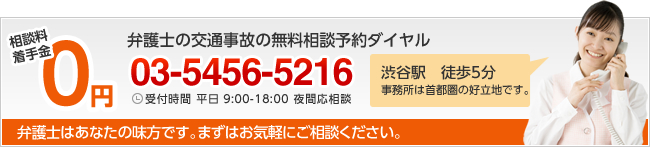
| ●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |