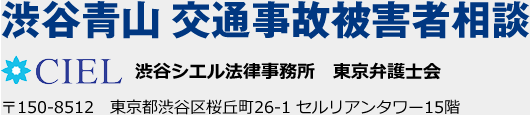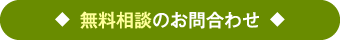【弁護士コラム】交通事故の被害者が陥りがちな誤解②
交通事故の被害者が陥りがちな誤解②
―「異議申立は認められない」は間違い―
 「異議申立は無駄」は誤解です
「異議申立は無駄」は誤解です
交通事故により後遺障害の申請を行ったものの、「非該当」とされた被害者は多くいます。又、想定外の低位な後遺障害しか認定されなかった方もいるでしょう。
その際、「異議申立はしても無駄」と周囲に言われ、諦めてしまう方が少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。
初回認定に問題があれば異議申立をする価値がある
自賠責保険の後遺障害等級は、医師の診断書や検査結果などをもとに審査されますが、必ずしも初回の認定が正しいとは限りません。
症状が診断書に記載されていない、必要な検査が行われていない、事故後の症状の経過が追えないなど、初回認定時に見落としや情報不足があるケースは少なくないのです。
こうした場合、正当な判断を得るためには異議申立が極めて重要です。
記載や資料不足が認定を妨げる
例えば、診断書の「症状経過欄」に、毎月同じスタンプだけが押されているだけの例もあります。これでは事故との因果関係や症状の持続性を確認できず、正確な審査が困難となります。
諦めず工夫すれば、結果は変わる
しかし、だからこそ異議申立には意味があります。私の経験でも、自賠責保険に2度異議申立を行い、2度目で後遺障害等級が認定されたケースや、異議申立を2回行った後、自賠責紛争処理機構に申し立てて認定が覆ったケースがあります。このように、一定の時間と労力を要することもありますが、必ずしも長期化するとは限りません。
症状と医学的所見が整合し、説得的な資料が揃っていれば、1度目の異議申立で認定が覆るケースも多くあります。重要なのは、初回認定の問題点を正確に把握し、それに対応する資料や医師の意見書、検査結果などを的確に提出することです。丁寧な準備こそが、認定結果を変える鍵となります。
思い込みで諦めないことが大切
「異議申立は通らない」というのは思い込みに過ぎません。認定結果に疑問があるなら、問題点を丁寧に洗い出し、必要な対応を講じることで正当な評価を受けることが可能です。諦める前に、ぜひ冷静に検討してください。
【2025年7月31日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
では、そんなにお気に入りだった愛車をなぜ手放したの?と思われるかもしれませんが、さす がに17年も乗り続けると、司法研修所で真っ赤なベンツを知っていた同期の弁護士に、「まだ同じ車に乗っているの?」と言われたり、自分でも、もう寿命だ ろうな。と感じたりたことが切っ掛けでした。
例えば、少しメンテナンスをさぼると、消耗品のリートが不具合を起こし、急にウインカーが出なくなったりしたため、怖くなってしまったのです。
それに、仕事上、交通事故の案件を多く扱っているので、ちょっとしたことで簡単に交通事故被害を起こすことを痛感していた事も大きかったです。 いつ事故に遭うかもしれないという不安を抱えながら運転を続けることに気疲れしてしまったのだと思います。
Part1 最近驚いたことーまさかの欠席判決?

民事裁判では、被告が初回期日に答弁書を出さずに欠席すると原告の請求どおりの判決が下されます。これが欠席判決ですが、被告にとっては大打撃です。そのため被告に付いた弁護士は必ず初回期日前に答弁書を裁判所に提出して争う姿勢を見せます。
ところが、被告から答弁書の提出がないまま初回期日を迎えた事件がありました。
このまま被告が出廷しないと欠席判決が言い渡されてしまう!とあり得ない事態に首を傾げながら、原告代理人として第1回期日に出廷すると、午前10時の指定時間になっても被告も被告の弁護士も現れません。
法壇上では裁判官が席に付き、私も原告席に着席し、書記官も被告が現れるのをじっと待っていましたが、5分経つ頃には静寂な法廷内におかしいぞ!という空気が流れ始め、まず裁判官が口を開き、こちらに向かって、被告には代理人(=弁護士)は付いていないのでしょうか?事前に連絡はありませんでしたか?と聞くので、こちらには何の連絡もありません。
弁護士は付いているはずですが連絡がないので分かりません。と答えると、書記官が廊下に出て事件番号や被告の名前を呼びながら被告を探すも反応無し。裁判官は仕方なく、原告は訴状を陳述しますね。被告は出廷しないので訴状の内容を擬制自白したものとして結審します。と言い、一週間後に判決の言い渡し期日が指定されました。
欠席判決は民事訴訟法には書いてあるものの実際に経験するのは初めてだったので、非常な驚きでした。原告側は労せずして請求が認められるので喜ぶべきだったかもしれませんが、欠席判決を貰う弁護士の不名誉を考えると、つまり自分が被告の代理人だったらと思うと恐ろしい!というのが実感。
被告は弁護士に依頼しなかったのだろうか?だったら自分が出廷しないといけないのに一体どうしたのだろう?あり得ない!と悶々としながら帰りました。
後日談ですが、この事件、実は被告には弁護士がちゃん付いていたのですが、その弁護士の所属事務所の手続きミスにより、答弁書を出し忘れたのだとか。
何ともお粗末ですが、被告側では、判決言い渡しまでの期間内にその事に気付き、被告の弁護士から焦った声でこちらにも連絡が入りました。その弁護士さん、裁判所には期日を再開して貰います。と言って申立書を提出したり大変な思いをして、やっと欠席判決を阻止出来たという結果でした。同じ弁護士としてヒヤヒヤさせられた驚くべき初回期日でした。
(Part2に続く)
お気軽にお問合せ下さいませ
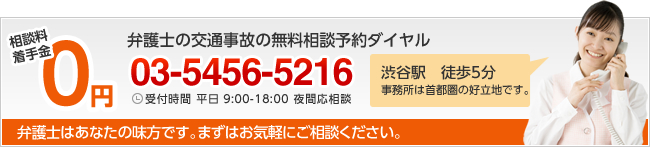
| ●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |