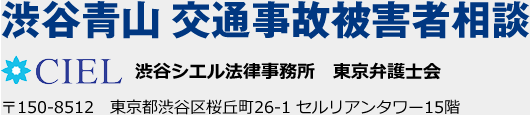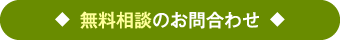【弁護士コラム】交通事故の被害者が陥りがちな誤解①
交通事故の被害者が陥りがちな誤解①
―「可動域制限=後遺障害」ではないという現実―
 交通事故に遭い、バイクや自転車で転倒してしまった際、多くの被害者の方が脚(下肢)に重大なケガを負うことがあります。
交通事故に遭い、バイクや自転車で転倒してしまった際、多くの被害者の方が脚(下肢)に重大なケガを負うことがあります。
とくに股関節、膝関節、足関節といった「下肢の三大関節」を負傷した場合、入念な治療を受けたとしても、痛みや可動域の制限といった不具合が後に残ってしまうケースは少なくありません。
そして、そのような不具合を抱える被害者の多くが、「事故前のように膝が曲がらなくなった」という理由で、自賠責保険の後遺障害等級の認定を目指すことが多い印象です。しかし、ここに一つ大きな誤解が潜んでいます。
「曲がらない」だけでは後遺障害と認められない
自賠責保険における後遺障害の等級認定には、厳格な基準があります。
たとえば、膝の可動域が健側(=負傷していない側)の1/2以下あるいは3/4以下に制限されているなど、客観的で明確な数値基準を満たしていなければ、「機能障害」として認定されることはありません。つまり、「以前より動かしにくい」「ちょっとしか曲がらない」という主観的な訴えだけでは、認定は極めて困難なのです。
被害者の方がこうした厳しさを知らずに、「下肢の後遺障害」→「機能障害(=可動域制限)」という文言だけを頼りに申請を進めてしまうケースは、実務でも少なくありません。
実は「痛み」による認定の方が現実的な場合も
一方で、可動域制限と並んで残ることが多いのが「痛み」です。膝や股関節などに慢性的な疼痛が残る場合、それが「局部に頑固な神経症状を残すもの」あるいは「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級または14級に認定される可能性があります。
とくに、12級の認定を受けるためには、医師の診断やMRI、X線などの他覚的所見が求められますが、症状と医学的所見が一致していれば認定されるケースは少なくありません。可動域制限だけに固執するよりも、痛みという観点からも後遺障害の申請を準備することが、認定の可能性を広げるカギになるのです。
【2025年7月1日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか