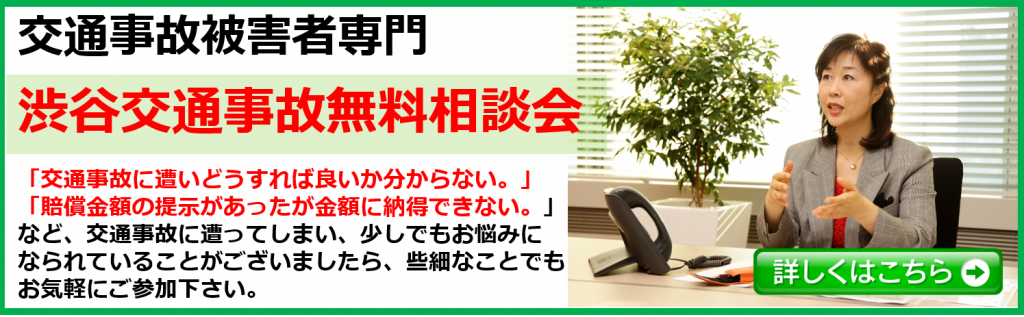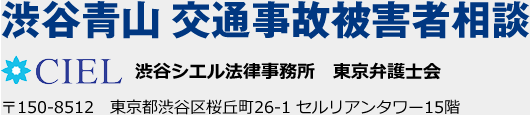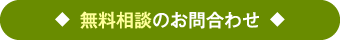【バイク事故判例⑮】バイクで直進中、交差点で出会い頭衝突をし、顔面に醜状障害(後遺障害12級)が残った44歳男性のケース
(令和 2年1月28日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル 2066号1頁等)
関係車両
バイク(原動機付自転車)vs普通乗用車
事故の状況
事故現場は、信号機のある十字路交差点。北方向から対面信号の青色表示に従って交差点に進入した原付バイクと、西方向から対面信号の赤色表示を無視して交差点に進入した加害車両が出合い頭に衝突し、原付バイクの運転者(被害者)は、衝突地点から5mほど跳ね飛ばされた。尚、被害者はヘルメットを着用していたが、救急隊到着時には、ヘルメットは離れた位置に落ちていた。
けが(傷害)
骨盤骨折、外傷性くも膜下出血、肺挫傷、顔面骨折及び顔面挫傷等
入院等の期間
①入院4ヶ月(125日)
②通院約1年9ヶ月(実日数は不詳)
後遺障害
顔面の醜状障害(12級14号)
頭痛、右顔面~後頭部のしびれ感・感覚低下(14級9号)
過失の割合
バイク0%、乗用車100%
判決のポイント
①過失割合(過失相殺)
被害者は新聞販売店の店長。外貌醜状については、外貌醜状の位置・形状(右眼右側に3cmの線状痕)、被害者の年齢(症状固定時46歳)、職業等を考慮すると、それによって原告の労働能力が低下したとまでは認められないとされ、神経症状(右顔面から後頭部にかけてのしびれ感など)についてのみ労働能力喪失率を5%とする逸失利益を認めた。但し、神経症状は将来的に馴化等を通じて症状が改善される可能性があるとし、労働能力喪失期間を10年に制限して逸失利益を算定した。
②慰謝料(後遺障害分)
外貌醜状は、それによって労働能力を喪失したとまでは認められないとしても、顔面に人目につく線状痕が残ったことによる精神的な苦痛は多大であると考えられるとされ、500万円と認定された。
小林のコメント
 大きな怪我だった割には、比較的軽い後遺障害が認定されるに留まったという印象です。実際の裁判では、5級相当の高次脳機能障害も被害者側から主張されましたが、裁判所は、事故直後に意識レベルの低下がみられなかった事や症状経過等を踏まえ、「高次脳機能障害の症状の経過としては,不自然・不可解」と述べ、被害者に「高次脳機能障害が残存したと認定するのは困難である」として否定しました。
大きな怪我だった割には、比較的軽い後遺障害が認定されるに留まったという印象です。実際の裁判では、5級相当の高次脳機能障害も被害者側から主張されましたが、裁判所は、事故直後に意識レベルの低下がみられなかった事や症状経過等を踏まえ、「高次脳機能障害の症状の経過としては,不自然・不可解」と述べ、被害者に「高次脳機能障害が残存したと認定するのは困難である」として否定しました。
慰謝料は、12級の通常の慰謝料(290万円程度)に比し高額な金額が認められたものの、被害者にとっては高次脳機能障害様の症状がメインの後遺症だったと思われることからすると、判決の結果は不本意であったろうと想像します。
(平成30年1月12日札幌地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)
関係車両
バイク(大型自動二輪車) 対 四輪車(普通乗用自動車)
事故の状況
事故現場となった道路は13メートル幅の幹線道路。バイクは交差点を右折後、幹線道路に進入したが、そこに路外の駐車場から出てきて右折進行しようとしていた乗用車がいたため、衝突し、右に転倒した。
けが(傷害)
腰背部打撲傷、両膝関節捻挫、右膝半月板損傷、両股関節挫傷等
治療期間
約1年2ヶ月(通院のみ)
後遺障害
自賠責保険の等級認定は、左股関節捻挫後の左股関節痛につき14級9号(「局部に神経症状を残すもの」に該当する。)
判決のポイント
①過失割合(バイク10%、乗用車90%)
裁判所は、原告(バイク)にも、右折先道路の確認を怠った過失があると判断しましたが、被告(乗用車)については、「特に、路外から道路に進入しようとする車両の運転者には,道路上の車両の走行を妨害しないように車両を道路内に進入させる義務があり,被告には原告よりも重い義務が課されていた」との理由で、90%の過失を認定しました。
②右膝半月板損傷、両股関節唇損傷の発生の有無
原告(バイク)は、本件事故によって右膝半月板損傷、左右股関節唇損傷の傷害を負い、同部位にいずれも12級13号の後遺障害(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)が残ったので、後遺障害等級は併合11級であると主張しました。
これに対し、被告(乗用車)は、原告の右膝には事故前から加齢による変性所見があった、左右股関節唇損傷が明らかになったのは事故から3年以上経過後だったこと等を理由に、右膝半月板損傷や両股関節唇損傷は、老化や事故以外の外傷によって発生したと反論しました。
裁判所は、まず半月板損傷について、原告の右膝の半月板損傷は右膝内側半月板後角の変性断裂であること、スポーツ外傷のような大きな外力で断裂が起こることは少なく日常生活レベルでの捻挫や軽微な外傷で発症することが殆どであることを理由に、事故との因果関係を否定しました。
一方、股関節唇損傷については、股関節唇損傷の多くは,臼蓋形成不全や股関節インピンジメント(FAI)などの骨形態異常を原因として生じるが原告の両股関節に骨形態異常があったとは認められないし、経年によって股関節唇損傷が生じる可能性は非常に少ない事を主な理由に挙げ、事故との因果関係を肯定しました。
③後遺障害の程度
裁判所は、上記に続けて、原告には左右の股関節唇損傷の傷害によりそれぞれ後遺障害等級12級13号相当の疼痛が残存し,あわせて併合11級相当の後遺障害が残存したと判断しました。
小林のコメント

①過失割合について
本件の乗用車のように駐車場から道路に出てきた車両は路外進入車といわれますが、路外進入車については、道路交通法上、次のように規定されています。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない」(道交法25条の2第1項)。裁判所が、「被告には原告よりも重い義務が課されていた」と述べたのは、このような法規の存在を前提にしています。
また、本件の現場道路は交通量の多い幹線道路だったので、路外車にはより一層、進入先道路の安全を確認すべき義務があったといえます。
②膝内側半月板後角の変性断裂、股関節唇損傷について
バイク運転者は53歳で、検査画像上、右膝や左股関節に加齢性(老化)の異常所見がありました。そのため、同部位の怪我は事故によるものか否かが争点となりました。この点につき、裁判所は、上記のとおり膝内側半月板後角変性断裂と呼ばれる膝半月板損傷に関する医学的知見と、股関節唇損傷に関する医学的知見に基づき、膝については事故との因果関係を否定し、股関節については反対に、事故との因果関係を肯定しました。
事故によって受傷した部位に加齢性の異常がある場合は、しばしば事故との因果関係が問題となりますが、本件はその典型例といえます。
【2023年11月21日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
 バイク(オートバイ、二輪車、原動機付自転車、単車)に乗車中の事故は、ヘルメット以外に身体を守るものがないため、重症化しやすいです。
バイク(オートバイ、二輪車、原動機付自転車、単車)に乗車中の事故は、ヘルメット以外に身体を守るものがないため、重症化しやすいです。
警視庁の交通事故統計(2020年中)によると、最悪の結果を招く原因となる損傷主部位は、頭部、胸部、腹部が大部分を占めるそうです。また、死亡事故の25パーセントで、事故時にヘルメットが脱落していたそうです。
このため、被害を軽減させるには、
①ヘルメットのあごひもをしっかり締める
②胸部プロテクターを着用することが大切である
と呼びかけられています。
よくあるバイク事故のケース
バイク事故の賠償問題を扱う中で多いと感じるケースは、交差点における直進中のバイクと右折自動車との衝突事故です。その他にも、自動車の左側にいて開いたドアにぶつけられたり、車線変更時の接触事故などが見られます。
バイクは車体が小さいので、自動車からは見えにくく、特にバイクが後方から走行してくると、後方への注視が十分でない事と相俟って、事故になりやすいのだと思います。
バイク事故の様々な怪我
バイク走行中の衝突は全身への衝撃が大きい上、転倒を伴うため、頭部外傷や骨折(足・鎖骨・肋骨等)、腕・肩~手首の脱臼や神経損傷など、様々な部位に怪我を負う事が多く、怪我も、生活への支障が大きな怪我が多くなりがちです。
バイク事故の治療の長期化
バイク事故では、骨折治療のために複数回の手術を受けたり、頭部外傷のために長期の経過観察を要する等、入院期間や通院期間が長引く傾向があります。
バイク事故は後遺障害が残るケースが多い
バイク事故では、生活への支障が大きな怪我が多いため、長期入院を余儀なくされた末に、後遺障害が残るケースが多いのも特徴的です。
バイク事故の様々な後遺症
後遺症の内容も、例えば、次のとおり多岐にわたります。
大腿骨(骨頭・頸部等)骨折後の股関節の機能障害、下肢の痺れ・疼痛
大腿骨骨折後の下肢短縮、膝関節機能障害
腕神経叢損傷後の上腕神経叢麻痺、肩(手・肘)関節の可動域制限
頭部外傷後の高次脳機能障害(記憶障害・失語・遂行機能障害・集中力低下等)
TFCC損傷による手首の関節機能障害、疼痛
脳挫傷後の片麻痺、味覚・嗅覚障害
下腿骨骨折後の足関節の機能障害
膝の靱帯損傷による膝痛
醜状障害(顔面・大腿・下腿等)
バイク事故の賠償問題は早期に始まる
バイク事故では入院治療が必要な事が多いため、その間、仕事を休まなければならず休業損害が発生します。退院が直ぐに出来て、直ちに仕事に復帰できれば良いですが、入院が長引く事が多いため、入院治療中から加害者(加害者の保険会社)に休業損害を支払って貰わなければ、生活が成り立たなくなる場合もあるため、深刻です。
このような理由で、バイク事故では、事故直後から、賠償問題が始まる事が多いです。
バイク事故の過失の割合(過失相殺)
又、バイク事故は走行中に起こる事が殆どのため、バイク側にも運転操作上の落ち度があるとして、加害者との間で、過失の割合が問題となる事が多いです。
その結果、例えば、バイク側にも2割の過失がある場合には、請求できる賠償金は、本来請求できる金額から2割減額されます。これを法律用語で、過失相殺(かしつそうさい)と言います。
バイク事故では刑事事件の記録が重要
このように、バイク事故では過失割合(過失相殺)が問題になる事が多いので、刑事記録の取り寄せが必須です。なぜならば、民事の賠償実務においては、示談・裁判を問わず、実況見分調書等の刑事記録に基づいて、道路状況や事故状況が判断され、過失の割合も判断されるからです。
刑事記録は、刑事手続きの終了後に、保管先の検察庁から取り寄せますが、保存期間の制限があるので、なるべく早い段階で、取寄せるべきです。
バイク事故の具体例(判例紹介)
バイク事故の実際の解決例
お気軽にお問合せ下さいませ
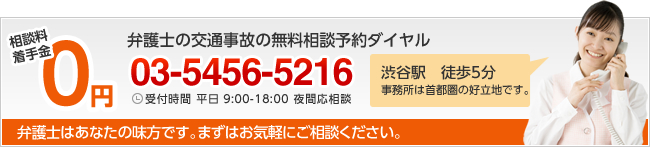
| ●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |