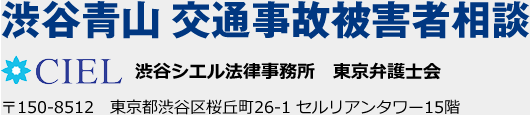【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例
(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等)
関係車両
バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車)
事故態様
事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突した。
けが(傷害)
顔面骨骨折、鼻篩骨粉砕骨折、顔面裂挫傷、頸部捻挫、第三頸椎棘突起骨折、左第五・六肋骨骨折、右強角膜裂傷、右網膜剥離、右増殖性網膜硝子体症、右外傷性白内障、右第二指中手骨骨折等
治療期間
入院6ヶ月、通院日数229日(症状固定までの期間は3年8ヶ月余り)
後遺障害
併合7級(右顔面醜状障害12級13号、右眼視力障害(手動弁)8級1号、右眼視野障害13級1号、嗅覚障害12級相当)
過失割合
バイク15%、自動車85%
判決のポイント
①過失割合
自動車の過失について、裁判所は、国道の中央分離帯付近で左方を十分確認すればより早い時点でバイクを発見でき事故を避けることができた、運転者が満68歳という高齢で左眼に白内障を患っていた事情(左眼の視力は矯正後0.6くらい)は、過失を認める方向に働くと述べ、その責任を認めました。
一方、バイク側にも、国道の制限速度(時速50㎞)を超える時速約68ないし78㎞前後で走行していたことや、東西道路(脇道)の存在を認識していたことから過失相殺を認め、双方の過失割合を上記のとおり認定しました。
②後遺障害逸失利益
逸失利益の請求に対し、被告(自動車側)は、被害者(バイク運転者)が事故後賃金カットされていないばかりか昇給していることを理由に、逸失利益の損害は発生していないと反論しました。
裁判所も、被害者が事故後に昇給していること等から、被害者が現に従事している業務(裏口の警備、書類等の運搬、郵便物の仕分け、ロビーの案内等)との関連では、後遺障害7級の労働能力喪失率56パーセントに達する程度までの不自由が生じている証拠はないと述べました。
ただ、同時に、被害者の後遺障害(顔面醜状、右眼視力障害、右眼視野障害、嗅覚障害)が、現在の業務に一定の影響を及ぼしていることは十分推認されるし、昇給・昇任・転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれもある、右眼の症状はむしろ将来悪化する懸念がある等と述べ、結論として、現在の職務に従事し得る限り、その労働能力喪失率は7級の喪失率56パーセントの3割として逸失利益の算定を行うのが相当であると述べました。
また、被害者は、定年(60歳)前の55歳以降は「専任行員」となり年収も半分に減ることとなっているがそうした条件で雇用関係が継続されるか否かは定かでないとして、55歳以降はむしろ症状固定時の賃金センサス(産業計・企業規模計・学歴計30歳~34歳男子労働者平均給与額)を基礎に、56パーセントの労働能力喪失率で逸失利益の算定を行うのが相当であると述べました。
その結果、55歳までは症状固定時の年収を基礎に、55歳から就労可能年である67歳までは賃金センサスの年収を基礎に、合計約2500万円の逸失利益を認めました。
小林のコメント

本件のように事故後に収入減少がない場合は、後遺症に起因する財産上の不利益はなく、逸失利益は認められないとする考え方もあります。
しかし、「例えば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしている結果であると認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがある場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情があれば、逸失利益を認める余地がある」とする最高裁判例があります(最三小判昭56.12.22)。
この最高裁の考え方からすると、事故後に減収がなくとも特段の事情があれば逸失利益が認められます。
本件の裁判所は、この最高裁と同じ考えに立って逸失利益を認めた上で、労働能力低下の程度(労働能力喪失率)については、後遺障害等級による労働能力喪失率を参考に、被害者の職業、年齢、後遺症の部位・程度等を総合的に考慮して判断したものと理解できます。
裁判では、事案ごとに具体的な事情を踏まえて逸失利益の算定が行われるので、その一例として取り上げました。
【2023年9月11日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか